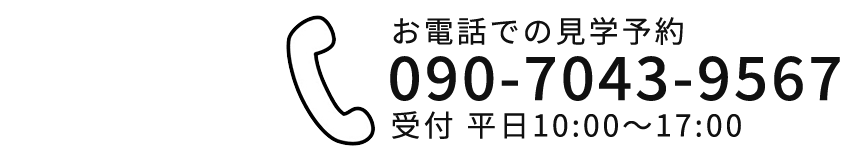お寺の歴史は古いものです。これは誰もが知っている事実で、歴史あるお寺であれば何百年も前に開基され、そこから本堂などの施設の補修や修復、建て替えなどを経ながら、代々にわたり継承されてきたことは言うまでもありません。
そのため、現代人の私たちは、そこにある「〇〇家 代々の墓」といったお墓についても、相当昔から続いているものだと自然に認識していますが、実際にはお墓の歴史はそれほど長くないことに驚かされます。
意外と短い?お墓の歴史
火葬が主流になったのは昭和時代から
もともと日本では土葬が主流であったことをご存じの方も多いと思いますが、それが現代で主流となっている火葬に変わり、火葬が土葬を上回るようになったのは、なんと昭和に入ってからだと言われています。これには驚かれる方も多いでしょう。
墓石の歴史は江戸時代中期から
また、お墓に関して墓石を建てるようになったのは江戸時代の中期以降からであり、その頃はまだ土葬が中心であったため、一つのお墓に埋葬できるのは一人か夫婦など二人程度だったそうです。それが昭和に入り、戦後の火葬の普及に伴って、ひとつのお墓に先祖代々の複数の遺骨を納めることができるようになり、火葬への移行が増加するタイミングに合わせて全国的に広まっていったのです。
現代の「先祖代々のお墓」の実態
このように、現代の「先祖代々のお墓」の歴史は、多くの方が想像しているほど大昔からある形態ではなく、昭和以降にようやく現代の形になり、拡大していったものなのです。
そう考えれば、「お墓」のかたちは、決して不変のものではなく、長い歴史の中でその時代その時代に合わせて、これまでも少しずつ変化してきたのだと思います。
現代のお墓事情の変化
新しい選択肢の増加
現代においても、まさにお墓の転換期にあり、墓じまいの増加や、永代供養の合同墓・樹木葬などを選ぶ人が増えるなど、これまでとは異なるニーズや選択が増えているのもごく自然な流れです。
習慣や文化の変化
そして、お墓の形態が変われば、それに付随する習慣や文化も変わると言われています。具体的には、お墓参りの風習として春と秋のお彼岸やお盆に参拝し、花を供え先祖を供養するという習慣も、これからの時代に合わせて変化していくかもしれません。
血縁を超えた新しい絆
またお墓については、一般的なお墓から合葬墓や樹木葬へと形が変わるだけでなく、最近では血縁にこだわらず友人同士で同じ合葬墓に入ることを希望する方も増えています。つまり、どんなお墓に入るかだけでなく、誰と同じお墓に入るのかという選択肢も変わってきているのです。
社会情勢が迫る変化
人口減少と単身者の増加
ここまで「お墓」の変化について説明してきましたが、日本の人口減少や婚姻組数の減少はまぎれもない事実であり、時代が自然にお墓のスタイルを変えたというよりも、変化を迫られて転換期を迎えていると言えます。つまり、今後もこの傾向はさらに拡大していくことでしょう。
現実的な課題への対応
残念ながら死亡者数は増えていきます。その中には身寄りのない方や単身者の割合も非常に多くなり、代々受け継がれてきたお墓を継承することが難しくなるだけでなく、自分自身のお墓を管理しお参りしてくれる親族がいない方もいます。
こうした状況を考えれば、「墓じまい」の準備や、お寺が管理や供養を行ってくれる永代供養の合同墓・樹木葬を生前に契約する方が増えているのも、まったく不思議ではありません。むしろ当然の流れともいえるでしょう。
これからの時代に向けて
日本社会が今置かれている状況に合わせて、私たち一人ひとりが、過去の日本で当たり前とされてきた風習や習慣をリセットし、これからの世代に向けて現代に合った形やスタイルを選択していくことが求められています。
気力と体力があるうちにしっかりと情報を集め、少しずつでも考え、行動していくことが大切なのかもしれません。さらに、家族や周囲ともよく話し合っておくことで、より安心できる選択につながるはずです。

永代供養をお考えの方は、お近くのお寺にご相談されることをお勧めします。それぞれのお寺で提供される永代供養の内容や費用は異なりますので、複数のお寺を比較検討することで、ご自身に最適な選択肢を見つけることができるでしょう。