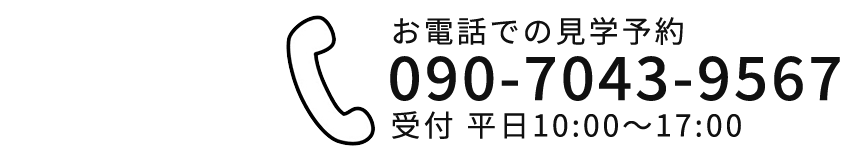近年、全国的に増加している「墓じまい」。高齢化社会の進行とともに、中高年層の間では、自身の健康問題に次ぐほど関心の高い話題となっています。テレビや新聞、インターネットなど、さまざまなメディアでも「墓じまい」に関する特集や情報が取り上げられることが多くなり、もはや珍しい言葉ではなくなりました。
しかし、この「墓じまい」については、誤ったイメージや理解を持っている人もいるのが現状です。ここでは、特に多く見られる二つの誤解について、ご紹介したいと思います。
まず一つ目の誤解は、「墓じまいをすることは、先祖に対して失礼になるのではないか」というものです。
たしかに、代々受け継いできた立派なお墓を、自分の代で撤去してしまうというのは、心理的に大きな決断です。「先祖を粗末に扱うようなことをしてはいけない」「自分の代で終わらせるのは罰当たりではないか」といった気持ちになるのは、自然な反応だと思います。
しかし、実際にはこの考え方こそが大きな誤解なのです。
もし、墓じまいをせず、そのままお墓を残して自分もそこに納骨されたとしたら、その後に誰も管理する人がいなくなってしまえば、そのお墓はやがて「無縁墓」となってしまいます。無縁墓とは、親族による管理や供養がなされず、放置されてしまったお墓のことです。誰もお参りに来ず、清掃もされず、やがては墓石が汚れ、苔が生え、朽ちていってしまうような状態になります。
「墓石は頑丈だから大丈夫だろう」「放っておいても何とかなる」と思っている方もいますが、実際には経年劣化は避けられません。特に日本は地震が多く、地盤の動きで墓石がずれてしまったり倒れてしまったりすることもあり、定期的な確認や状況次第では、メンテナンスも必要です。
つまり、誰にも引き継がれず、朽ちていくお墓を放置することの方が、はるかにご先祖様に対して不本意な結果になるのではないでしょうか。きちんと墓じまいを行い、改めて納骨先を整えて丁寧に供養するというのは、決して失礼なことではなく、ご先祖様への深い配慮に基づいた行動といえるのです。
次に、二つ目の誤解は、「墓じまいについてお寺の住職に相談するのは失礼ではないか」「住職が反対するのではないか」といったものです。
これについても、よくある誤解の一つです。「長年お世話になったお寺に対して申し訳ない」「お墓をなくすなんて、とても言い出せない」と感じている方は少なくありません。中には、実際に墓じまいを申し出た際に、高額な費用を請求されたという話を聞いたことがあるかもしれません。
もちろん、すべてのお寺がそうではありませんし、そのような例の多くは、後継者がまだ存在するにもかかわらず、檀家としてのお付き合いを早々に終えようとするケースに多いと言われています。単なる整理ではなく、「義務から逃れたい」というような印象を与えてしまう場合、トラブルが起きることもあるかもしれません。
しかし、丁寧に事情を説明し、今後の供養の形についても誠実に相談すれば、多くのお寺は理解を示してくださいます。むしろ、将来的に無縁墓となってしまうことを避けるために、早めに墓じまいの相談をしてもらった方がありがたいと考える住職も少なくありません。
なぜなら、無縁墓が増えれば、墓地の景観や管理にも支障が出ますし、最終的には撤去や処分を行わなければならなくなるからです。そうした作業には費用が発生しますが、お寺がすべてを負担するわけにはいきません。だからこそ、将来のことを見据えて、自ら責任をもって墓じまいを考えることは、むしろ協力的で感謝されることなのです。
このように、「墓じまい」は決して後ろ向きな行動でも、ご先祖様やお寺への非礼でもありません。それは、未来を見据え、ご先祖様への敬意を込めて、よりよい供養のかたちを整えようとする、前向きな選択といえるでしょう。